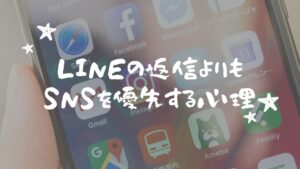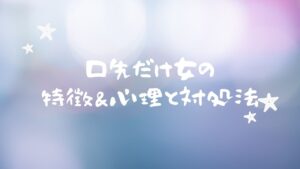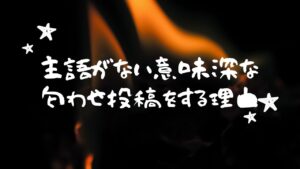「オレって仕事できるんだよね」「アタシは正直、周りより上だと思う」――そう語る人に限って、実は全然そうでもない…そう思った経験、ありませんか?
実はこれ、心理学の世界で「ダニング=クルーガー効果」として知られてる現象。
「能力の低い人ほど、自分の能力を過大評価しやすい」という心理的傾向のことです。
ポイントは、「自分が何を知らないか」を正しく理解するためには、ある程度の知識やスキルが必要ということ。
ところが、未熟な人ほどその“自己評価に必要な知識”が足りないため、現実以上に自信を持ってしまうんです。
なぜ「できない人」ほど自信満々なのか?
知らないからこそ「簡単そう」に見える
知識や経験が浅いと、物事の難しさや奥深さが見えません。
そのため「投資?そんなの簡単でしょ」みたいに、やたら自信満々になります。
これはいわゆる“無知の無知”状態。「自分がどれだけ知らないかすら分かっていない」ということです。
一方、経験を積んだ人ほど「自分にはまだ学ぶべきことがある」と自覚できる。だからこそ、むやみに自信を持ったりしないんですね。
他人と自分の違いが見えていない
実力がない人は、他人と自分のパフォーマンスの差をうまく見分けられません。
「まあ、みんなそんなもんでしょ?」と思い込んでしまうのは、自分を客観的に見る“メタ認知力”が足りないから。
だから、自分の失敗に鈍感だし、他人の優れた点にも気づきにくい。
逆に、有能な人ほど「他人は自分よりもっとすごい」と思える。そのギャップを知っているからこそ、謙虚でいられるんです。
「自分はできてる」と思ってるから、学ぼうとしない
自分を高く評価している人は、反省や改善の必要性を感じません。
フィードバックをもらっても「でも俺は合ってる」と受け流し、結果として同じミスを何度も繰り返します。
これはまさに「学ばない → 実力が上がらない → でも自信は高いまま」という悪循環。
一方、実力のある人は「もっとよくできるはず」と思っているため、常に成長しようとします。この差が、やがて大きな実力の差になっていくんです。
こういう人に出会ったとき、どうする?
相手が上司でも部下でも友人でも、こういうタイプと関わるのは、正直しんどい。
でも、感情的になって正面からぶつかると、ほぼ確実にこじれます。
ここでは、現実的な5つの対処法をご紹介。
真っ向から否定しない
このタイプは、自分を否定されると猛烈に反発してきます。正論は通じません。
対応ポイント
・「なるほど、そういう考えもあるんですね」と一旦受け止めるフリをする
・「ちなみにこんなデータもありますよ」と、さりげなく事実で軌道修正
質問で気づかせる
指摘すると怒るので、問いかけで“考えさせる”ほうが効果的。自分で考えたことは、意外と納得しやすいんです。
例:
✕「それ間違ってるよ」
〇「そのやり方だと、うまくいくポイントってどこだと思います?」
期待しすぎない
「成長してもらおう」と本気で向き合うと、こっちが疲れるだけ。
このタイプとは“適切な距離感”で接するのがベストです。
心の持ちよう:
・説得ではなく「マネジメント」だと割り切る
・必要以上に深入りしない
第三者や仕組みに頼る
感情論になりがちな相手には、中立な仕組みや数字が効果的。
本人に直接言わなくても、外部の評価で“ズレ”を浮き彫りにできます。
例:
・上司やリーダーにレビューを頼む
・客観的な指標(KPIや評価制度)を使う
無理せず、距離を取ることも選択肢
どうしても改善されず、関わることで自分が疲弊するなら、戦略的撤退もアリです。
例えば:
・関係性を見直す
・プロジェクトを変えてもらう
・配属の相談をする
他人を変えるより、自分の対応をアップデート
残念ながら、“自信だけは一人前な人”を根本的に変えるのは難しいです。
でも、私たちの関わり方を変えることで、無駄な消耗を防ぎ、状況をコントロールすることはできます。
エネルギーを注ぐべきは、自分を高めてくれる人たちとの時間。
「関わる価値のある人」に、リソースを使いましょう。